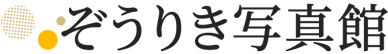これまで多くのお客様の大切な「思い出」をカタチにしてまいりました。

館内には、ぞうりき写真館のこれまでのカタチが飾られています。

あなたの大切な日にお越しくださいませ。
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
行事に関する豆知識
お宮参り
お宮参りとは子供が生まれて初めて神社(産土神=うぶがみ)に参拝し、数珠をいただき、子供の長寿と健康を祈る行事です。生後1ケ月ほど経過すればす赤ちゃんの体調やお母さんも回復するので母子共に安定する時期であり、男児は、31日目、女児は32日目に行うのが通例となっています(地方によって様々ですので事前にお調べいただいたほうがよいでしょう)。
ただあまり日数に深くこだわらず、あくまでも赤ちゃんの体調を優先し、天候が穏やかで赤ちゃんのご機嫌な日やご両家のご家族が揃う日を優先に考えるの一番良いかもしれませんね。
七五三
男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳にあたる年に晴れ着で氏神様に詣でる行事です。
七五三は、もともと宮中や公家、武家で行われていた行事が広く行われるようになったもので、七五三と呼ばれるようになったのは、明治時代になってからと言われています。
3歳は、男女ともにもう赤ん坊でないという意味から髪を伸ばし始める「髪置き」、5歳は男の子が初めて袴をつける「袴着」、7歳は女の子が着物の付け紐を取り去り帯に替える、「帯解(帯祝い)」の祝いがその由来だそうです。
現代では該当年齢の子供に晴着を着せて11月15日に神社へ参拝しするようになりましたが、最近では数え年(年齢+1)でなく満年齢祝われる方も多く、参拝される日も前後の日付がとても多くなってきました。やはり節目の記念日にはご家族で集まれる日が良いでしょう。
初節句
子どもが生まれて初めて迎える節句が「初節句」です。
女の子は3月3日「桃の節句」、男の子は5月5日「端午の節句」で、女の子には雛人形、男の子には兜飾りや武者人形を贈って飾ります。
赤ちゃんが生後1~2ヶ月で首がすわっていないような場合は、初節句のお祝いを翌年に延ばすのが通例のようです。
ちなみによく耳にする端午(たんご)とは一体
元は午(うま)の月(旧暦5月)端(はじめ)の午の日を節句として祝っており、後に5が重複するこの月を端午の節句としたそうです。また端午の節句は菖蒲の節句とも言いますが、この菖蒲は勝負にかかっています。なんとも男の子の日らしいですね。
対して女の子の場合は桃の節句、ひな祭りです。
古来中国より伝わった上巳(じょうし)の節句が正しいのですがこの節句が旧暦3月3日、ちょうど桃の花が咲く頃でもあり、「桃の節句」という美しい名前が生まれたそうです。
桃の節句では女の子の健やかな成長を祝う行事で、お雛様(雛人形)は赤ちゃんの身に降りかかろうとする災厄を、代わりに引き受けてくれる守り神様とされており、平安時代以前の貴族の子女が天皇御所を模して遊んでいたものの流れを汲んでいます。
百日祝い
子供の生後百日目に行う行事ですね。
「食べ物に困らないように」、「丈夫な歯が生えるように」、また「頭が早く硬くなるように(赤ちゃんの頭は大変柔らかいため)」などの願いが込められています。
百日という日数にこだわらず、生後3~4ヶ月の歯が生え始めたらくらいの期間に行うのが一般的です。